中学生が家庭科の授業で取り組む「絵本作り」は、自分の考えを形にする貴重な機会です。しかし「どんなネタにすればいい?」「どうやって構成を考えるの?」と迷うことも多いでしょう。
この記事では、初心者でも簡単に取り組める絵本のネタ10選と、ストーリー作りのポイントをわかりやすく解説しています。対象年齢ごとのアイデアや、失敗しないためのコツ、実際に使われた実例まで網羅しているので、課題対策にもぴったりです。
この記事でわかること:
-
1〜3歳・4〜6歳・小学生向けの絵本ネタとストーリーの違い
-
絵本作りで失敗しないために押さえるべき3つのポイント
-
実例とテンプレートを使った効果的な構成方法
-
絵や色使いに自信がない人でも魅力的な作品にするコツ
中学生家庭科の絵本作りネタ10選!初心者でも使えるアイデア集

中学生が家庭科の授業で取り組む絵本作りは、ただの工作ではなく「相手の気持ちを考える力」や「伝える力」を育てる貴重な体験です。ただ、実際に「どんなネタで絵本を作ればいいの?」と悩む生徒も多いですよね。特に初心者の場合、対象年齢やテーマ、構成の作り方まで、何から手をつけていいかわからず困ってしまうこともあるはずです。
そこでこのパートでは、「初心者でもすぐに取り組める絵本ネタ10選」として、年齢別に具体的なテーマやストーリー例をご紹介します。1〜3歳、4〜6歳、そして小学生にも応用できるアイデアまで幅広く取り上げているので、どの年齢層向けに絵本を作るか決まっていない方も安心して読めます。中学生らしい視点で、相手に楽しんでもらえる絵本作りの第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
1〜3歳向けのシンプルなテーマ例
1〜3歳の子どもたちは、まだ言葉の理解が未発達なことが多いため、絵本の内容は「シンプルで繰り返しがあること」がポイントです。この年齢では、日常の身近な出来事や音の響きが楽しい言葉を使ったストーリーが人気です。
たとえば、「おさんぽたんけん」や「ごはんのじかん」など、日常の一場面を切り取ったテーマは親しみやすく、想像もしやすいためオススメです。「いぬさん、にゃーにゃー、かえるさん」といった動物の鳴き声を繰り返すリズムのある文章も、この年齢の子にぴったり。ページごとに同じセリフが出てくる構成にすると、読んでいて自然と真似をしてくれるので、読み聞かせにも向いています。
また、色や形をテーマにした「まるちゃんどーこだ?」のような探し絵の要素を入れると、親子で楽しめる工夫にもなります。家庭科の授業で制作する際には、絵の描きやすさやページ数(6ページ程度)を考慮しながら、絵とセリフのバランスを取りましょう。難しく考えすぎず、素朴なテーマでOK。大切なのは、読み手を想像しながら優しい気持ちで作ることです。
4〜6歳向けの人気ストーリー構成
4〜6歳になると、子どもたちの想像力や感情の表現がぐっと豊かになります。そのため、物語には「問題→解決」のような簡単なストーリー構成を取り入れると効果的です。「あったかいふくをきたくまさん」「おおきなにんじんをぬきたいねずみさん」のような、ちょっとした困りごとを主人公がどうやって乗り越えるのかという内容が好まれます。
この年代では、キャラクターに個性を持たせたり、冒険や挑戦などの“目的”を持たせることで、ストーリーにぐっと深みが出ます。また、仲間が増えたり、助け合ったりする展開を取り入れると、「協力することの大切さ」などの教育的なメッセージも自然に伝えることができます。
例えば、うさぎが風船を追いかけて空を飛ぶ「ふうせんうさぎのぼうけん」などは、夢があり、読み手のワクワク感を引き出せるテーマです。絵の部分でも、感情がわかりやすく伝わる表情や動きを意識して描くと、より印象に残る作品になります。
家庭科の授業で提出する場合、「主人公が誰か」「何をしようとしたのか」「何が起きたか」「どう解決したか」の4つを意識して構成することで、先生からの評価も高くなりやすいでしょう。
小学生向けにも応用できるネタ
家庭科の絵本作りで「小学生向け」に仕上げたい場合は、少し長めのストーリーでも理解されやすいため、テーマ選びに幅が出てきます。この年齢になると、「友情」「ルール」「自己肯定感」など、道徳的な要素を軽く含んだ内容も受け入れられやすくなります。
たとえば、「にじいろのさかなのともだちさがし」や「ぼくのまちにはひみつがある」といったストーリーは、ちょっとした日常の疑問や葛藤を描きながらも、最後には前向きな気持ちになれるような構成が好まれます。また、環境問題や思いやりといったテーマも、柔らかい言葉と絵で表現すれば子どもたちに自然と伝わります。
この場合は登場人物の関係性や、結末の意味を少し深めて描くと、より心に残る作品になります。とはいえ、複雑になりすぎると読みづらくなるので、ストーリーはあくまでシンプルに、登場人物も2〜3人以内にするとバランスが取りやすいです。
家庭科の評価としては、「読む人のことを考えて丁寧に作られているか」「テーマがしっかりしているか」などもポイントになります。小学生向けは幅広いテーマが使える分、読み手を意識した表現が大切になります。
中学生家庭科の絵本作りネタで失敗しないためのコツ

家庭科の絵本作りは、自由度が高いぶん「どう作ればいいかわからない」「何を描けばいいのか迷ってしまう」といった声も多く聞かれます。せっかく時間をかけて作ったのに、相手に伝わらなかったり、評価がイマイチだったりするとがっかりしますよね。特に中学生は、自分の感性と読者(幼児など)のニーズとのバランスを取ることにまだ慣れていないため、失敗しやすいポイントもあります。
しかし、あらかじめいくつかの「コツ」を押さえておけば、スムーズに楽しく絵本を完成させることができます。このパートでは、失敗を避けるために知っておきたい基本的なポイントを3つ紹介します。「誰のための絵本か?」「どんなことを伝えるか?」「構成はどうするか?」といった絵本作りの根本に関わる視点から、初心者でもしっかり形にできるヒントをお届けします。
対象年齢を明確にする
絵本作りを始めるとき、まず最初に決めておくべきなのが「誰に向けた絵本か」ということです。中学生の家庭科の課題として提出する場合、多くは「幼児向け」とされることが多いですが、実際には年齢によって興味を持つ内容や理解できる表現が異なります。
たとえば、2歳の子には言葉の意味よりも「音の響き」や「繰り返し」に楽しさを感じますが、5歳になると「物語性」や「感情表現」にも関心を持つようになります。そのため、対象の年齢をはっきりさせないままストーリーを考えてしまうと、読み手にとって分かりにくく、楽しめない絵本になってしまう可能性があるのです。
対象年齢を明確にすることで、「使う言葉」「話の長さ」「絵の表現」なども自然と決まってきます。制作前にまず「2歳児が読むとしたら?」「4歳だったら?」と、読み手の年齢に合わせてイメージを膨らませましょう。対象がはっきりすれば、絵本に必要な要素も自然と見えてきて、制作がぐっと楽になります。
伝えたいことを一つに絞る
絵本は短いページ数の中で、何かを伝える「小さな物語」です。だからこそ、1冊に詰め込めるテーマはひとつ、多くてもふたつまでに絞ることが大切です。よくある失敗例として、「友情もルールも家族も全部伝えたい!」と欲張ってしまい、結果的に読んだ人にとって中途半端な印象になることがあります。
中学生の家庭科の課題で評価される絵本とは、「誰が読んでもわかりやすく、内容がはっきりしている」作品です。たとえば、「やさしさってなに?」というテーマを選んだなら、そのやさしさがどうやって伝わるか、どう行動で表すかということだけに集中して構成しましょう。
シンプルにするほど読みやすく、伝わりやすくなります。特に読み手が幼児の場合は、メッセージをシンプルにすることが大前提。複雑な内容は伝わりにくくなるだけでなく、読むのも疲れてしまいます。
「この絵本で何を一番伝えたいか?」を明確にすることで、ストーリーやイラスト、キャラクターのセリフなども一本筋が通った仕上がりになります。まずは1つの大事なメッセージに焦点を絞る。それだけで絵本作りの難しさはぐっと減っていきますよ。
ストーリー構成は「起承転結」で考える
中学生にとって、「物語を作る」というのは意外と難しい作業です。絵本のストーリーも、何も決まりがないと自由すぎて、どこから手をつければいいかわからなくなってしまいます。そこで役立つのが、昔からある「起承転結」というストーリーの基本構成です。
「起」は物語のはじまり、登場人物や状況を紹介します。「承」で問題が起きたり変化があり、「転」で思いがけない出来事が起きて盛り上がり、「結」で物語がまとまって終わる。これを意識するだけで、話の流れがぐっとスムーズになり、読む人にも伝わりやすくなります。
例えば、「おもちゃを壊してしまった子ども」が主人公の場合、「起」でおもちゃが大好きなことを紹介し、「承」で壊してしまって落ち込み、「転」で家族や友達の助けで修理してもらい、「結」で大切にする気持ちを学ぶ…という流れにできます。
このように起承転結を使うことで、自然なストーリー展開ができ、読み手を飽きさせずに最後まで楽しませることができます。ページ数が限られる家庭科の絵本作りでは特に、話を整理するためにこの構成を使うことがとても役立ちます。
中学生家庭科の絵本作りネタに役立つ実例とテンプレート

絵本作りにおいて、「何から始めたらいいかわからない」と悩む中学生は多いはずです。アイデアはあるけれど、実際にどんな構成にすればよいのか、どんな素材を使うのがよいのか…と、いざ作る段階で迷ってしまうのはよくあることです。そんな時に役立つのが、過去の実例やテンプレートです。実際に他の生徒が作った絵本や、ページごとの構成例を見れば、「自分にもできそう!」という気持ちが湧いてくるでしょう。
このパートでは、家庭科の授業で評価された絵本の具体例や、6ページ構成のテンプレート、さらには作品の見た目をよくするための素材・色づかいのコツなどを紹介していきます。実例に触れることで、アイデアに広がりが出るだけでなく、より効率的に作品を完成させるヒントが得られるはずです。まずは完成のイメージを持ち、自分なりの工夫をプラスしてみましょう。
実際に使われた課題作品の紹介
中学生の家庭科で提出された絵本作品の中には、シンプルながらも非常に評価が高かったものがあります。たとえば、「たまごくんのぼうけん」は、たまごがいろいろな食材と出会いながら自分の役割を知るという内容で、短いながらも起承転結がしっかりしており、登場キャラクターの表情や動きがユーモラスに描かれていました。読んだ子どもたちからも「たまごがかわいかった!」「こんな風に料理になっていくのが面白い」と好評だったそうです。
また、「なきむしうさぎのだいぼうけん」という作品では、泣き虫なうさぎが一人でおつかいに行き、途中で困ったり助けられたりしながら成長していく様子が描かれていました。この作品では、場面ごとの感情の変化がしっかりと描かれていて、「子どもにとって共感しやすい内容だった」と先生からも高評価を得ていました。
こういった実例を見ると、「難しいことをしなくても、読み手の心に届く作品は作れる」ということがわかります。まずは他人の作品を真似するのもOKです。そこに自分らしいキャラクターや言葉を加えていけば、自然とオリジナリティのある作品に仕上がっていきます。
6ページ構成にまとめる方法
絵本のページ数は、授業の指定で「6ページ以内」や「見開き3回分」といった制限があることがよくあります。そんな限られた中でストーリーをうまくまとめるには、あらかじめページごとの内容を簡単にメモしておく「構成表」を作るのが効果的です。
たとえば、6ページの基本構成は以下のようになります。
- 1ページ目:主人公の紹介(例:くまのコロちゃんが登場)
- 2ページ目:出来事が起こる(例:森で道に迷う)
- 3ページ目:困りごとが発生(例:おなかがすいて元気が出ない)
- 4ページ目:助けが現れる(例:リスが食べ物をくれる)
- 5ページ目:問題解決(例:無事に家に戻る)
- 6ページ目:結末とメッセージ(例:「ありがとうって大事!」)
このようにページごとの目的を決めておくと、無駄な場面がなくなり、スッキリと読みやすい絵本になります。また、場面の切り替えを明確にすることで、読む人が話の流れをしっかり追いやすくなります。
短いページ数でもストーリーがしっかりしていれば、読み応えは十分あります。時間をかけて長く作るよりも、内容を絞って簡潔にまとめるほうが、むしろ印象に残る絵本になることもあるのです。
素材や色づかいのポイント
絵本作りで意外と差がつくのが、使う「素材」や「色づかい」です。ストーリーがよくても、絵が薄かったり、色が単調だったりすると、読む側の印象がぼやけてしまいます。家庭科の絵本作りでは、決してプロのような技術を求められているわけではありませんが、「丁寧に作られているかどうか」はとても重要な評価ポイントです。
おすすめなのは、色鉛筆やクレヨン、水性ペンなどを組み合わせて使うこと。部分的にフェルトや折り紙を貼るなど、少し立体的な工夫を入れると、見た目に変化が出て楽しい絵本になります。特に小さな子ども向けの絵本では、明るくはっきりした色を中心に使うことで、視覚的にも興味を引きやすくなります。
また、背景がごちゃごちゃしすぎるとキャラクターが目立たなくなるので、背景はシンプルに仕上げるのがコツ。色に迷ったら、赤・青・黄色といった基本色をベースに考えるとよいでしょう。
「上手に描く」よりも「見やすく、伝わりやすい」絵を意識することが大切です。絵が苦手な人でも、色のバランスや素材の使い方を工夫することで、十分に魅力ある作品を作ることができます。
中学生家庭科の絵本作りネタまとめ
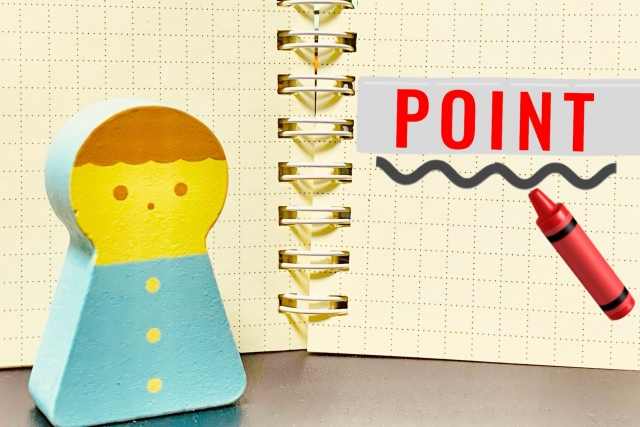
この記事のポイントをまとめます。
- 中学生の家庭科絵本作りは、相手の年齢に合わせたテーマ設定が重要
- 1〜3歳向けは音や繰り返しを意識したシンプルな内容が効果的
- 4〜6歳向けには冒険や挑戦などのストーリー性が求められる
- 小学生向けには感情や道徳的要素を軽く盛り込むのがポイント
- 絵本制作で失敗しないコツは「対象年齢の明確化」から始まる
- テーマは1つに絞ることで、内容がぶれずに伝わりやすくなる
- 起承転結を意識した構成でストーリーが整理され読みやすくなる
- 過去の実例を参考にすることで、自分のアイデアが広がりやすい
- 6ページ構成にする際はページごとの役割をあらかじめ決めておく
- 色づかいや素材の工夫で絵が上手くなくても印象に残る作品にできる
絵本作りは、自由な発想と優しさが活きる素敵な課題です。難しく考える必要はありません。大切なのは「読む人を思う気持ち」と「伝えたいことを形にする工夫」です。
この記事を参考に、あなたらしい一冊を楽しみながら完成させてください。

