ホワイトボードが欲しいけれど、スペースやコストの問題で導入をためらっている方へ。本記事では、「ホワイトボードの代わりになるもの」に注目し、今すぐ試せるおすすめ代用品や選び方のコツをわかりやすく解説します。
手作り素材からデジタルツールまで、目的に合わせて最適な選択ができるようサポートします。
この記事でわかること:
-
ホワイトボードの代わりになるもののメリットとは?
-
手作り&市販のおすすめ代用品10選
-
代用品を選ぶときに重視すべきポイント
-
安全に使うための設置場所の注意点
ホワイトボードの代わりになるものを使う理由とメリット

日常のさまざまな場面で便利に使えるホワイトボードですが、実際に導入しようとすると、スペースの確保や価格、設置の手間といった現実的な問題が立ちはだかることも少なくありません。特に自宅や小規模オフィス、限られた予算内で運営される教育現場では、「本格的なホワイトボードを買うほどではないけど、何かしらの代用手段が欲しい」と感じることが多いのではないでしょうか。
そんなニーズに応えるのが、「ホワイトボードの代わりになるもの」です。近年では100均などで簡単に手に入る素材から、デジタルツールまで、さまざまな代用品が登場しており、それぞれに異なるメリットがあります。この記事では、「なぜあえて代用品を使うのか?」という視点から、3つのポイントに分けてその利点を詳しく解説していきます。
設置スペースがいらないコンパクトな代用品が便利
ホワイトボードの最大の課題のひとつは、設置にある程度のスペースを要することです。壁に固定するタイプであれば穴を開ける必要があり、賃貸物件では難しいケースもありますし、スタンド式のホワイトボードでも、置き場所に悩むことはよくあります。特に狭い部屋や物が多い空間では、「ここにホワイトボードがあったら便利だけど、場所がない…」と断念してしまう方も多いはずです。
その点、代用品は「使うときだけ出して、使い終わったら片付ける」という柔軟な運用が可能です。たとえば、透明のクリアファイルに白い紙を挟み、ホワイトボード用マーカーで書けば、簡易的なホワイトボードとして機能しますし、使用後はそのまま引き出しに収納できます。また、ラミネート加工した紙であれば、繰り返し書き消しができて耐久性も高く、子どもの勉強用にぴったりです。
さらに便利なのが、「静電気シート」や「ホワイトボードシート」の存在です。これらは軽量で薄く、壁やガラスなどにぴたっと貼り付けるだけで、まるで本物のホワイトボードのように使用できます。使い終わったら簡単にはがして再利用できるものも多く、折りたたんで保管できるため持ち運びにも適しています。会議室やセミナー、子ども部屋など場所を問わず対応できる点が、非常に大きなメリットです。
また、デジタルツールである「Zoomのホワイトボード機能」や「NearHub」のようなタブレットデバイスを活用すれば、完全に物理的なスペースから解放されるという選択肢もあります。画面上で書いて共有するため、場所を取らず、遠隔地の人ともリアルタイムで情報交換が可能です。
このように、「ホワイトボード=大きくて重いもの」という固定観念を取り払えば、実は日常の中で使いやすくてスマートな選択肢がたくさんあるのです。
低コストで使えるものが多く経済的
ホワイトボードを新しく購入しようとしたとき、意外と費用がかかることに驚いた方も多いのではないでしょうか。特に大型のホワイトボードやスタンド付きのタイプ、さらには電子ホワイトボードとなると、1万円以上の出費になることも珍しくありません。それに加えて、専用のマーカーやイレーザーなどの備品も必要となり、トータルコストは思っている以上に高額になります。
その点、代用品を使うことで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。たとえば、模造紙は1枚数十円から購入できますし、100円ショップではラミネートシートやホワイトボード風の透明シートが手に入ります。クリアファイルに白い紙を挟んでマーカーで書けば、それだけで即席のホワイトボードが完成します。どれも身近な素材ばかりで、すぐに用意できるのが魅力です。
また、再利用できる代用品を選べば、さらに経済的です。ラミネート加工を施した紙やアクリルボードなどは、何度も書き直せるため、日々のメモや学習、打ち合わせなどに繰り返し使えます。一度作っておけば長期間使用できるため、消耗品を頻繁に買い替える必要もありません。
環境面でもプラスです。使い捨ての付箋やメモ帳に比べて、ゴミが減り、ペーパーレスの意識も高まります。加えて、静電気シートやデジタルツールを活用すれば、インクや紙を使わずに済むため、さらに環境負荷を抑えることができます。
学校やオフィス、家庭内での情報共有など、ホワイトボードを必要とするシーンは多いものの、毎回のコストが気になるという場合には、こうした低価格で入手・運用できる代用品が非常に有効です。少しの工夫でコストを抑えつつ、同じような効果を得られるのは、まさに一石二鳥と言えるでしょう。
家庭・教育・ビジネスシーンで使い分けできる
ホワイトボードの代わりになるものの魅力の一つは、その「用途の広さ」にあります。家庭、教育現場、ビジネスのどの場面でも、それぞれの目的に合わせた使い方ができる柔軟性があるため、一つの代用品が複数のシーンで役立つというのが大きな特徴です。
まず、家庭での活用例を見てみましょう。リビングの冷蔵庫や玄関に静電気シートを貼って、家族への伝言板や買い物リストとして使えば、スマホをわざわざ開かなくてもすぐに情報を確認できます。子どもがいる家庭では、壁にラミネート紙を貼って、ひらがなや九九の練習、自由なお絵描きスペースとして使うことで、楽しみながら学習習慣が身につきます。汚れたら拭くだけでOKという手軽さも、親としては助かるポイントです。
教育の現場では、模造紙やホワイトボードシートを使ってグループワークに活用したり、教室に常設できない場合でも、必要な時に広げてすぐに書き込める環境を整えることができます。さらに、黒板が古くて見えにくいといった課題がある学校では、アクリルボードや透明シートなどを使って、より視認性の高い情報伝達手段として機能します。
ビジネスの現場では、より高度な機能を求められるケースもありますが、それにも代用品は対応可能です。たとえば、ZoomやMicrosoft Teamsのホワイトボード機能を活用すれば、リモート会議でもホワイトボード感覚でアイデア出しや説明ができます。また、Miroのようなオンラインホワイトボードは、世界中のメンバーとリアルタイムで共同作業ができる強力なツールです。これにより、物理的なボードを用意する必要がなくなり、情報共有のスピードと柔軟性が格段に向上します。
このように、使う場面によって「何が最適な代用品か?」を考えることで、ホワイトボードに代わるさまざまな選択肢が見えてきます。1つの高価な製品に頼るのではなく、それぞれの目的に合ったツールを賢く選ぶことで、より快適で効率的な作業環境を整えることが可能になります。
ホワイトボードの代わりになるもののおすすめアイテム10選

「ホワイトボードが欲しいけれど、設置が難しい」「もっと手軽に使えるツールが欲しい」という声に応えるのが、身近な素材やアイディアで代用できる“ホワイトボードの代わりになるもの”たちです。最近では100均アイテムや日用品、さらには無料で使えるデジタルツールまで、工夫次第で様々な代用品を使うことができます。
このセクションでは、アナログからデジタルまで、今すぐ試せるおすすめアイテムを10個紹介します。どれも特別な準備がいらず、コスパが良く、しかも用途に応じて選べるものばかりです。特に家庭や教育現場、リモートワークの場面で活躍するアイテムを中心に選びましたので、気になるものがあればぜひ取り入れてみてください。
模造紙・ラミネート紙など手作り系の代用品
「ホワイトボードがない!」というときに真っ先に活躍するのが、模造紙やラミネート紙といった手作り系の代用品です。これらはコストも非常に低く、必要な分だけ使えるのが大きな魅力です。
まず模造紙は、広い面に自由に書き込むことができ、プレゼンやグループワークにも最適です。壁に貼っておけば、参加者全員が視認しやすいホワイトボード代わりとして活躍します。一方、ラミネート紙は紙を透明フィルムで保護することで、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりが可能になります。
ここで紹介するおすすめ代用品:
-
模造紙(壁に貼って大きく使える)
-
ラミネート加工したA4〜B4サイズの紙
-
ホワイトボード風の紙(文具店や100均で購入可能)
-
手作りのホワイトボード(紙を厚紙に貼り、透明ファイルでカバー)
これらは子どもと一緒にDIYする楽しさもあるうえ、用途に応じて自由に大きさやデザインを変えられるという点で、非常に実用的です。
アクリル板やクリアファイルなど家庭にあるもの
「今あるもので何か代用できないかな?」というときは、家庭にある文具や素材を見直してみるのがおすすめです。特にアクリル板やクリアファイルは、意外にもホワイトボードのように使える優れたアイテムです。
アクリル板は、透明で硬質な素材なので、ホワイトボード用マーカーで書いても簡単に消すことができます。壁に立てかけたり、デスクの上に置いたりと、自由なレイアウトが可能です。クリアファイルも同様に、白い紙を挟んで表面に書くだけで即席のボードになります。
ここで紹介するおすすめ代用品:
-
透明アクリル板(ホームセンターや通販で入手可能)
-
クリアファイル+白紙(超定番の即席ホワイトボード)
-
プラスチック製の下敷き(表面がツルツルしていればOK)
これらのアイテムは見た目もすっきりしていて、収納にも困りません。また、道具としての汎用性も高く、使わないときは本来の用途に戻して使えるという点でもコスパに優れています。
NearHubやMiroなどのデジタルホワイトボード
近年注目を集めているのが、物理的なスペースを使わずにホワイトボード機能を提供してくれる「デジタルホワイトボード」です。これは特にリモートワークやオンライン学習の場で力を発揮するアイテム群で、パソコンやタブレットを使って、画面上で書き込みや共有ができるのが最大の特長です。
たとえば「NearHub」は、専用のデバイスを使って、リアルタイムで共同作業や画面共有ができる高性能なデジタルホワイトボードです。また「Miro」や「Zoomのホワイトボード機能」などは、アプリやウェブ経由で無料・簡単に使えるツールとして多くの企業や教育機関で採用されています。
ここで紹介するおすすめ代用品:
-
NearHub S Pro(高性能な一体型デジタルホワイトボード)
-
Zoomのホワイトボード機能(リモート会議で活躍)
-
Miro(オンライン共同作業に最適なツール)
これらは初期費用こそかかる場合もありますが、長期的にはペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化にもつながるため、導入する価値は十分にあります。
ホワイトボードの代わりになるものの選び方ポイント

数あるホワイトボードの代用品の中から、自分にぴったりのアイテムを選ぶためには、いくつかのチェックポイントがあります。何となく手軽に使えそうだからと選んだものの、「すぐに消せない」「壁に貼れない」「思ったより小さくて使いづらい」といった後悔をしてしまうことも珍しくありません。
逆に、自分の目的に合ったものをしっかり選べば、日常生活や仕事、学習の効率を大きく向上させることができます。選ぶべき代用品は、使うシーンやスペース、共有の有無などによって異なります。たとえば、自宅でのToDoリストなら小さめの静電気シート、リモート会議ならZoomやMiroなどのデジタルツールが向いているでしょう。
このセクションでは、ホワイトボードの代わりになるものを選ぶ際に押さえておきたい「3つの選定ポイント」を紹介します。自分に最適なアイテムを見つけるために、ぜひチェックしてみてください。
使用目的に応じてサイズや機能を選ぶ
ホワイトボードの代わりになるものを選ぶ際に、まず重視すべきなのが「使用目的」です。ホワイトボードというツールは、使う人によって求める役割が大きく異なります。例えば、家庭での使用であれば買い物リストや家族への伝言を書き残すような使い方が中心になりますし、教育現場では板書や生徒とのインタラクティブな授業に活用されます。ビジネスシーンでは、アイデア出しやタスク整理、会議での情報共有といった役割が求められるでしょう。
こうした目的の違いに応じて、最適なサイズや形状、さらには機能性のある代用品を選ぶことが、失敗しないための基本です。たとえば、家庭内の冷蔵庫に貼っておきたいという場合は、A4サイズの静電気シートやマグネット式のホワイトボードシートが最適です。これらは簡単に設置・取り外しができるため、見た目もスッキリしていて、毎日の情報のやり取りに最適です。
一方で、学習用途には、広めのラミネート加工済みの用紙や、壁に貼るタイプのホワイトボードシートなど、子どもが自由に大きく書き込めるスペースを確保できるものが向いています。算数の図形問題や漢字練習など、繰り返し書いて消すことができるので、学習効率を高めるサポートになります。
さらに、ビジネス用途では、オンラインでのやり取りが増えている現在、「物理的な代用品」ではなく「デジタルホワイトボード」のニーズも高まっています。Zoomのホワイトボード機能や、NearHubのような一体型デバイス、Miroなどのコラボレーションツールを活用することで、遠隔地のチームメンバーともリアルタイムでアイデアを共有できます。
重要なのは、「とりあえず使えそうだから選ぶ」のではなく、「どのように使うかを具体的にイメージしてから選ぶ」ことです。サイズが小さすぎてメモしか取れない、逆に大きすぎて収納場所に困る、といったことを防ぐためにも、まずは利用目的を明確にして、それに合った機能とサイズを選びましょう。
消しやすさ・書きやすさ・耐久性をチェック
ホワイトボードの代用品を選ぶ際、多くの人が見落としがちなのが、「実際に書いて、消して、繰り返し使えるかどうか」という基本性能の部分です。どんなにオシャレで高機能に見えても、書き心地が悪かったり、消すのに力が必要だったり、すぐに表面が傷んで使えなくなってしまっては意味がありません。
まず、書きやすさに関しては、代用品の素材が大きく関係します。クリアファイルやアクリル板は表面が滑らかで、ホワイトボードマーカーがスムーズにインクを出せるため、比較的快適に書くことができます。ただし、安価なプラスチック素材や下敷きなどは表面がツルツルしすぎていて、手が滑ったり、線がかすれる場合があります。これを防ぐためには、事前に試し書きしてみることが重要です。
次に、消しやすさ。ラミネート紙やアクリル板、静電気シートなどは比較的インクが簡単に拭き取れる傾向にありますが、これも素材の品質に依存します。安価な素材だとインクが染み込んでしまったり、数時間後にはインク跡が残ってしまうこともあります。こまめな掃除が必要になるような素材は、日常的に使用するにはストレスが大きくなりがちです。
耐久性も重要な要素です。例えば静電気シートは便利ですが、使用回数が増えると粘着力が低下し、すぐに剥がれてしまうことがあります。アクリル板は長持ちしますが、落下などによる破損リスクがあります。また、ラミネート加工の用紙も、頻繁に折りたたんだり擦ったりすると、フィルムが剥がれたり傷が付いて使いにくくなってしまうことがあります。
これらの問題を避けるためには、「書いて・消して・再利用する」という一連の使用サイクルを想定したうえで、耐久性やメンテナンスのしやすさもチェックポイントに入れるべきです。実際に店頭で触ってみる、レビューを参考にする、複数回使用しても状態が保てるかを試してみるといった事前チェックが、長く快適に使える代用品選びにつながります。
貼り付け可能な場所や安全性を確認する
ホワイトボードの代用品を選ぶとき、意外に盲点となりやすいのが「どこに貼るか」と「安全性」の問題です。特に家庭での使用や教育現場など、多くの人が行き来する空間で使う場合、落下のリスクや壁へのダメージといった物理的なリスクを軽視してはいけません。
まず、貼り付けられる場所の確認は非常に重要です。ホワイトボードシートには「静電気タイプ」「マグネットタイプ」「粘着タイプ」など複数の種類があり、それぞれ対応できる素材の表面が異なります。たとえば、静電気タイプはガラスや冷蔵庫などの平滑な面には非常によく貼り付きますが、ざらざらした壁紙には使えません。マグネットタイプは金属面にしかつかないため、オフィスのパーテーションやスチール棚には使えますが、木の壁には不向きです。
次に、安全性。重いアクリル板やガラス製のボードを壁に立てかけて使用する場合、地震やちょっとした衝撃で倒れてしまう可能性があります。特に小さな子どもがいる家庭では、思わぬ事故につながるリスクがあるため、転倒防止対策や低位置への設置など、安全面に細心の注意を払う必要があります。
また、粘着タイプのシートは強力に貼り付けられる反面、はがすときに壁紙を破いてしまうことがあります。賃貸物件で使用する場合は特に注意が必要で、できるだけ「剥がし跡が残らないタイプ」や「再利用可能なタイプ」を選ぶようにしましょう。
さらに、デジタルホワイトボードのような電子機器を使う場合にも、設置場所の安全性は無視できません。たとえば、電源ケーブルを引っ掛けて転倒させてしまう、重さで棚がたわむ、熱がこもって機器の寿命を縮めてしまう、といったトラブルが考えられます。使用場所の広さや通気性、電源の位置なども考慮して、安全に使用できる環境を整えることが重要です。
このように、どれほど便利な代用品であっても、「どこで・どうやって使うか」をしっかりと想定しなければ、かえって危険を招くこともあります。使いやすさだけでなく、「安全に長く使えるかどうか」も含めて選択することが、後悔しないためのポイントです。
ホワイトボードの代わりになるもののまとめ
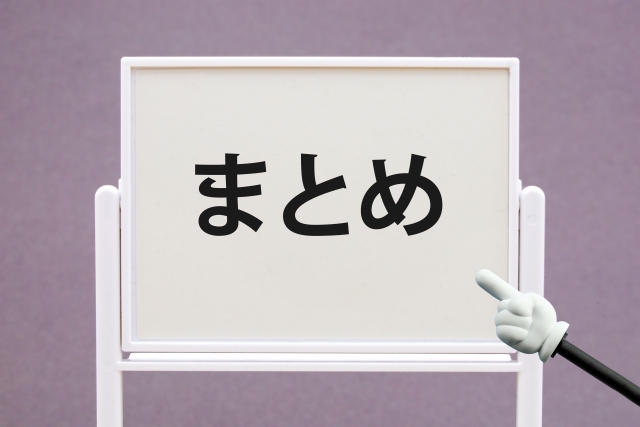
この記事のポイントをまとめます。
- ホワイトボードの代用品は、省スペースで使えるコンパクトなものが多数ある
- 模造紙やラミネート紙などの手作り代用品はコストも低く取り入れやすい
- クリアファイルやアクリル板など家庭にあるもので手軽に代用可能
- デジタルホワイトボード(Zoom、Miroなど)を使えば場所を選ばず効率的
- 利用目的に応じたサイズや設置方法の選定が重要
- 書きやすさ・消しやすさ・耐久性も代用品選びのカギになる
- 貼り付け可能な場所との相性や安全性を事前にチェックすることが大切
- 冷蔵庫やガラス、パーテーションなどの素材に合わせた選択が必要
- コスト削減と環境配慮の両立が可能な点も代用品の魅力
- 家庭・教育・ビジネスなど、シーンに応じた使い分けで効果を最大化
ホワイトボードの代わりになるものは、探してみると意外に身近なところに多く存在しています。わざわざ高価なホワイトボードを購入しなくても、手軽で実用的な代用品を上手に選べば、あらゆる場面で同等の効果が得られるのです。
自分に合った方法を取り入れ、快適で効率のよい情報共有・整理の環境を手に入れましょう。

